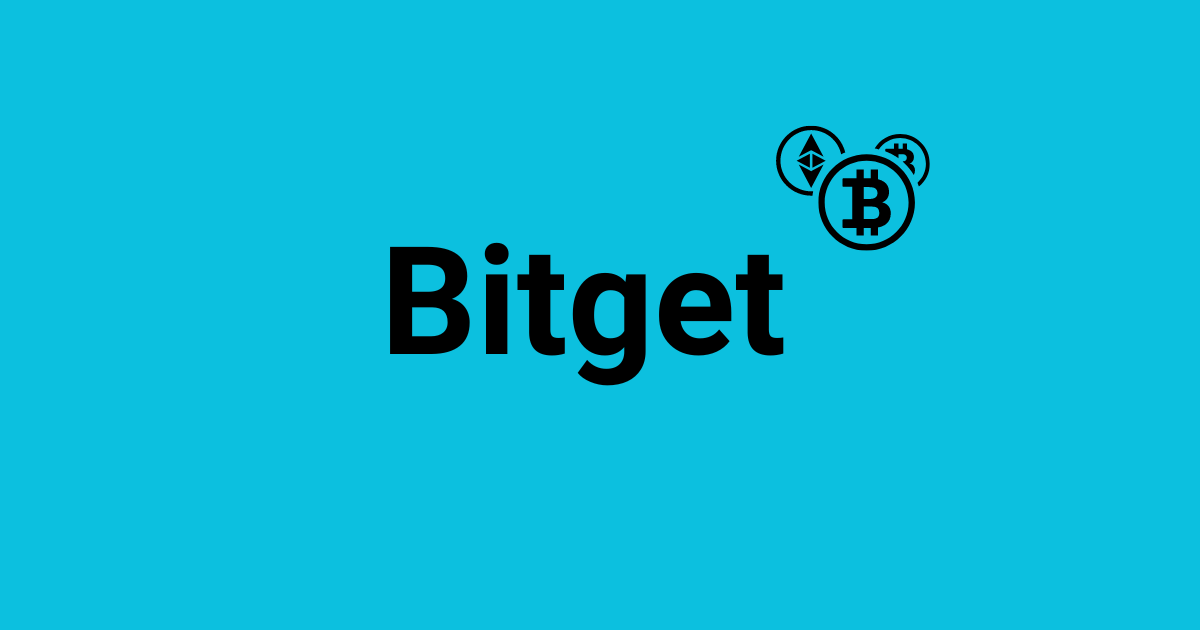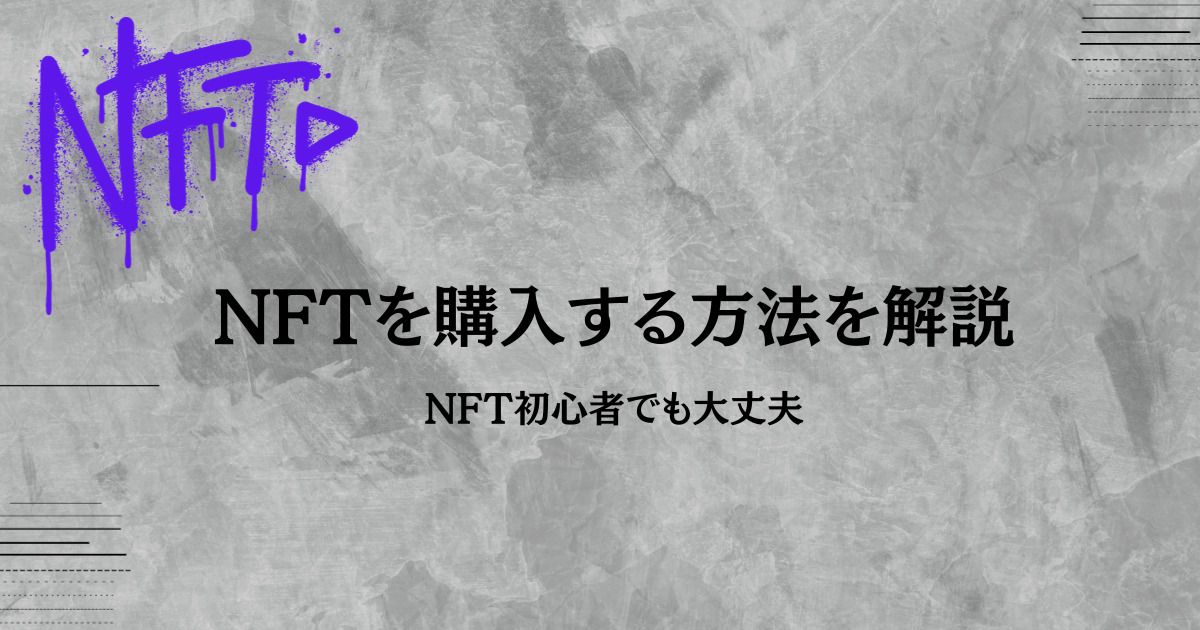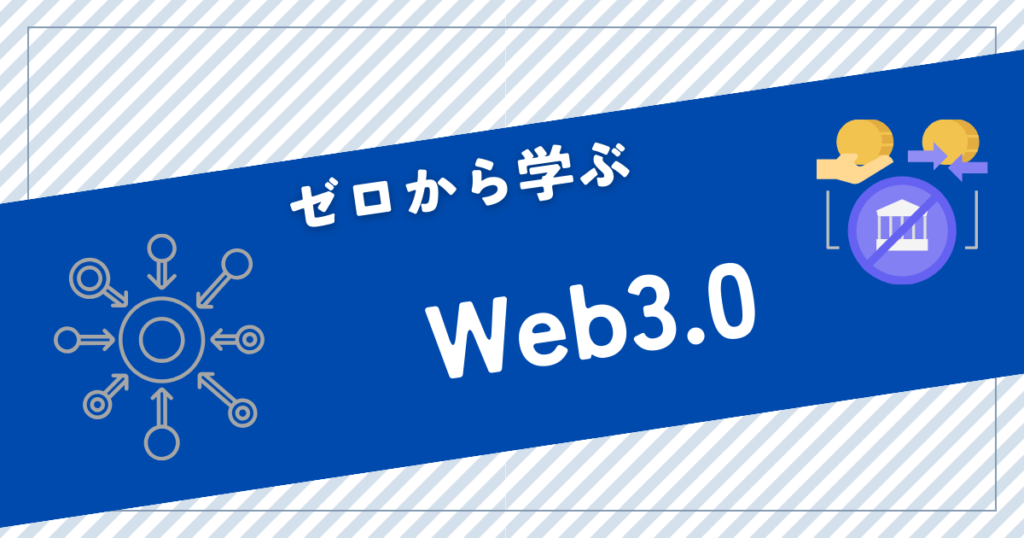
この記事を読まれている方は、

近年『NFT』、『WEB3.0』、『メタバース』などの言葉を聞くようになったけど具体的にどういう意味なんだろう?

初心者にも分かりやすく説明して欲しい。
感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
WEB3.0というのは、ブロックチェーンの技術を活用したインターネットの概念の事を指しますが、初心者の方はイメージしずらいですよね。
実際にWEB3.0は現時点で、そこまで世の中に浸透している単語ではありません。
特に日本はこの領域において、人材のみならず企業も足りていない状況にあります。
Web3について、「名前や特徴までよく知っている」(2.3%)、「名前や特徴をある程度知っている」(6.2%)、「名前だけは知っている」(21.2%)を合計すると約3割(29.7%)となった。約7割(70.3%)が「まったく知らない」と回答し、まだ多くの生活者がweb3について認知していないことが分かった。【図表1】また、web3の認知率は15~19歳の男性が最も高く、約半数(48.6%)が認知していることが分かった(「名前や特徴までよく知っている」(12.1%)、「ある程度知っている」(10.3%)、「名前だけは知っている」(26.2%)の合計)。 株式会社電通ホームページから引用
しかしながら、近い将来Web3.0が『当たり前』になる世の中がやってくる可能性が高いです。というか、もう既に浸透しつつあります。
実際に、日本の大手企業もWeb3.0に参入している事例が多くあります。
例えば『吉本興業』は近年メタバース市場に参入し、一般客がバーチャル空間でもお笑いを楽しめるようなイベントを企画しています。
この記事ではWeb3.0の概要と、これまでのWeb1.0、Web2.0の違いを説明します。
その上で、Web3.0の全体像を俯瞰した上で、詳細を深掘って行きます。
今回はWeb3.0について初めて触れる方にも理解できるところにフォーカスしましたので、是非最後まで読んでいただけると幸いです。
WEB3.0とは何か?
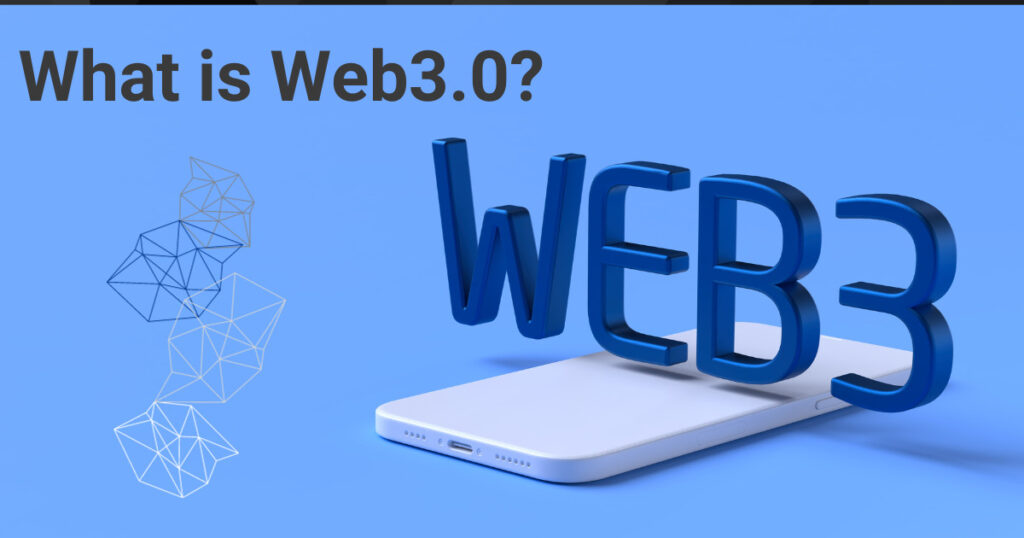
Web3.0とは、一言で言うと「ブロックチェーン技術を利用したインターネットの新しい概念」のことです
Web3.0の基盤であるブロックチェーン
ブロックチェーンを一言で表すと、以下の通りです。
ブロックチェーン
分散型ネットワークに暗号技術を組み合わせ、複数のコンピューターで取引情報などのデータを同期して記録する方法のこと。
ブロックチェーンは名前の通り、取引情報が格納された『ブロック』が過去から1本のチェーンのように繋がっている形で記録されています。
ブロックチェーン技術を使う事によって、取引データの改ざんや破壊する事が難しくなり、結果障害によってネットワークが停止する可能性が低くなるといったメリットがあります。
その為、今後はセキュリティーの高さが特に必要となる金融業での送金は勿論のこと、カーシェアリングや電力や上下水道などの様々な事業においてブロックチェーン技術が使われる可能性があります。
おそらく一言で言われても分からないと思いますので、仕組みについてもう少し噛み砕いて説明します。
ブロックチェーン技術は、まず、発生した取引情報を『ブロック』と呼ばれる記録に格納します。
ブロックには同時に『ハッシュ値』と呼ばれる1つ前に生成されたブロックの内容を示した値も格納されている状態です。
ハッシュ値
データ(テキストやファイルなど)を一定の長さの固定された文字列に変換したものの事を言う。ハッシュ値の大きな特徴としては、過去から未来に『一方向』であるという特徴がある。つまり、同じデータに対しては常に同じハッシュ値が生成されるものの、反対にハッシュ値から元のデータを復元する事は困難である。このような特徴がある事からハッシュ値は、データの改ざんを防ぐことを目的として使われることが多い。
このハッシュ値が格納されている事によって、仮に過去に生成した取引履歴の情報を改ざんしようとした場合に、変更したブロックから導き出されるハッシュ値は全く異なるものになります。
同時にブロックチェーンは1つの鎖のように繋がっている技術であるので、改ざんをした場合それ以降のハッシュ値も変更する必要があります。
しかし、それは事実上困難である為、ブロックチェーンの仕組みはデータの改ざんを防ぐことが可能となります。
このようにブロックチェーンが、『取引記録の書き換えや消去が決して不可能な、改ざんが非常な困難な技術』であることを理解いただけたと思います。
Web3.0は分散型インターネットを形成
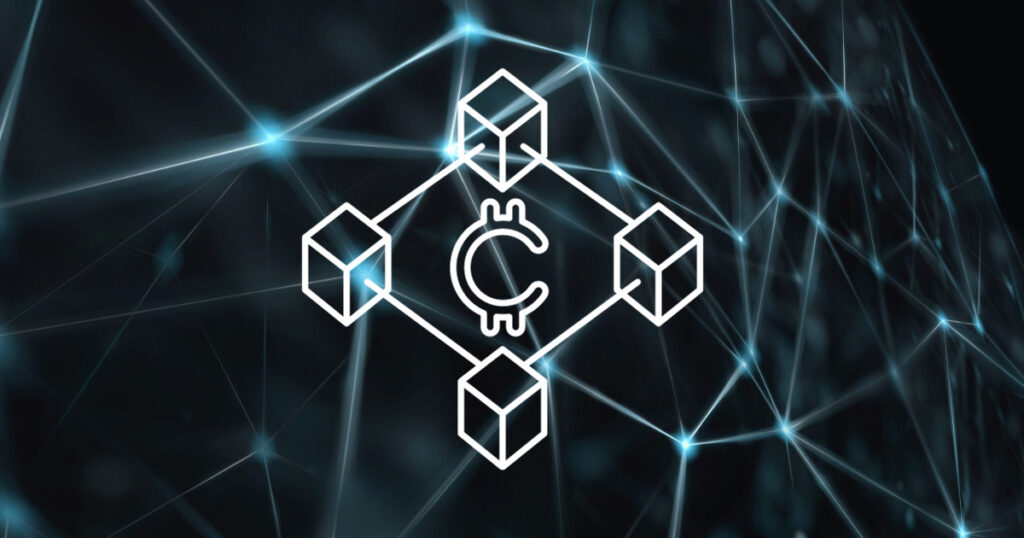
先ほどの話に戻しますが、Web3.0とは『ブロックチェーン技術を利用したインターネットの新しい概念』の事です。
ブロックチェーンの意味を知って、少しイメージ出来る様になったと思います。
Web3.0業界は元々『ブロックチェーン業界』と呼ばれていた位、ブロックチェーンが根底にある概念であることは覚えておきましょう。
そして、Web3.0は題名にある通り、ブロックチェーンを通じて『分散型インターネット』を形作っています。
これは、特定の企業や管理者に縛られることなく、データや情報を分散化することで個人でデータを所有することが出来ると言う事です。
これまでは、GAFAなどの巨大企業が個人のデータ(例えば購入履歴、ID、パスワード)を管理していましたが、Web3.0では自身でデータを『所有』できることが最大の特徴です。
Web3.0に至るまでの歴史(Web1.0〜3.0)
Web1.0の特徴
Web1.0とは、Webブームの一番最初の段階であり、1994年頃から始まりました。
95年にはMicrosoft explorer 95が登場し、世界的なブームが巻き起こりました。
Web1.0はWeb2.0と同様に中央集権的と言えます。
また、インターネットに誰もがアクセス出来るようになったものの、新聞や雑誌などの媒体をオンライン化しただけの、「見る」ことが中心の時代でした。
つまり、後に述べるWeb2.0のような、SNSを通じて友人や家族と相互にやり取りする事が中心ではなかったということです。
さらに、当時はPCが高額だった事もあり、一般家庭にまでは浸透しませんでした。
まとめると、Web1.0は中心にいる管理者が我々のような個人に『一方通行』に情報が流れていく仕組みと言えるでしょう。
Web2.0の特徴
Web2.0はWeb1.0の項目でも説明したように、個人間の相互のやり取りが活発となった時代のことを言います。
年代としては、2005年にTim O'Reilly氏がWeb2.0という言葉を提唱したのが発端です。
2005年~2021年までの期間がweb2.0の時代です。
現在は、Web2.0と後に説明するweb3.0の過渡期にある状況です。(Web3.0は2021年においてベンチャーキャピタルの投資額が過去最大だった為、Web3.0の時代は2021年からと言えるが、現在は完全にWeb3.0に移行したのではなく、Web2.0とWeb3.0の過渡期にある)
Web1.0とWeb2.0の違いとしては、『一方通行』な情報の移動が『双方向』になった事です。
世の中に浸透しているinstagramやtwitterなどは誰もアカウントを作成すれば利用する事ができ、友人や有名人の投稿にコメントやいいねを付ける事が出来ます。
Web2.0で相互が対話できるコンテンツが増え、ネットを通じて繋がりを感じられるというメリットはあるでしょう。
しかし、同時に誰もが情報をネットに書き込める時代になったため、どの情報を信じれば良いか分からなくなるというデメリットもあります。
また、Web2.0の時代では、GAFA(Google.Apple.Facebook.Amazon)が台頭し、個人情報をこれらのテックジャイアントが管理するという構図でした。
これらの巨大企業が情報を管理した事により、インターネットは格段に便利になりましたが、ユーザーの情報や住所などの個人情報が企業に流出してしまうという問題点があるのが現状です。
さらに、これらの企業がハッキングにあった場合、我々の情報が改ざんに合う可能性があり、いわば重要な情報が集中するがあまりリスクの分散化が出来ていない状態です。
Web3.0の特徴

これらのWeb2.0の問題点を解消すべく、誕生したのが近年話題となるWeb3.0のムーブメントです。年代としては、2021年~現在です。
Web3.0の大きな特徴は、ブロックチェーン技術を活用しているという事です。
また、GAFAなどの企業や国が中央集権的にデータを管理せずに、『分散化』されているという特徴があります。
そして、Web3.0では『P2P』というシステムを使う事で、仲介組織のサーバーを経由しなくても個人間でデータのやり取りをする事が可能となります。
P2P
Peer-to-Peerの略で、コンピュータやデバイス同士が通信する事で、ファイルや情報を共有する技術やネットワークの事を指す。第三者機関(企業や国)が情報管理するのではなく、個人(peer)同士で情報を共有する仕組み。
P2Pの位置付けとしてはブロックチェーン技術の一部と捉えて下さい。
ブロックチェーン技術は複数の既存の技術の組み合わせで出来ています。
Web3.0はWeb2.0のように、中央にいる管理者が個人情報を一元管理している訳ではないです。
そのため、管理者に対してサイバー攻撃をして、データベースに保管されている莫大なデータが抜き取られてしまうというリスクを未然に防ぐ事が出来ます。
Web1.0~3.0の比較表
Web1.0、Web2.0、Web3.0の大まかな違いを表にしました。
| 時期 | 形態 | 情報の流れ | コンテンツ | サービス | |
| Web1.0 | 1995年〜2005年 | 静的なWebページ(閲覧メイン) | 一方通行 | 読み取り専用 | Webサイト |
| Web2.0 | 2005年〜2021年 | SNS中心 | 双方向 | 誰もが情報発信者になれる | SNS、サブスクリプション |
| Web3.0 | 2021年〜 | ブロックチェーンの活用 | 双方向+自律的 | 分散して個と個がつながる | NFT、DeFi |
Web3.0の全体像、トレンドの技術
暗号資産

暗号資産
ブロックチェーン技術を利用した、円やドルなどの法定通貨とは異なるデジタル通貨の事を指す。暗号資産の特徴としては、銀行等の管理機関を通さずにインターネット上でやり取りをする事が出来ることである。
仮想通貨は国内の取引所と海外の取引所で購入する事ができますが、海外の方がレバレッジ倍率が高かかったり、取り扱う仮想通貨の種類が多かったり、色々進んでいます。
しかし、海外取引所は日本円で直接通貨を購入できないなど、使いこなすのが難しいので初心者の方はまず国内取引所を使ってみることをお勧めします。
国内取引所(Coincheck,bitFlyer)での仮想通貨の購入方法を見たい方は、下記の記事を参考にして下さい。
海外取引所(Bybit,Bitgetでの仮想通貨の購入方法を見たい方は、下記の記事を参考にして下さい。
NFT

NFT
代替できない「世界に1つだけ」のトークンの事を指す。NFTの大きな特徴は『非代替的』つまり替えが効かないということである。そして、ブロックチェーン技術を通して成り立っている。
NFTの理解が深まるように一例を挙げます。
友達と10円玉を交換する際は、10円の価値は変わらないので交換は成立します。つまり、代替性があると言えるでしょう。
しかし、この場合はどうでしょう。
2枚の同じ白Tシャツがあるとします。
片方のTシャツは何も書かれていないTシャツ、もう片方のTシャツには大谷翔平選手の直筆サインが書かれていたとしましょう。
この場合、2つの価値は異なるので替えは効かない、つまり『非代替的』であると言えます。
大谷翔平選手の直筆サインと同じように、デジタルデータにも『固有のアドレス』が割り振られている為、一見見た目が同じものでもアドレスが異なることから本物と偽物の判別が付きます。
また、NFTはブロックチェーン技術を使っていることから、データの改ざんが非常に困難となっています。
その為、デジタルデータの改ざんが容易に出来て、そのデータ固有の価値がなくなってしまうのを防ぐ事が出来ます。
唯一性を担保することが出来るということです。
NFTの概要と購入方法は下の記事を参考にして下さい。
DeFi

DeFi
ブロックチェーン技術を利用した、分散型金融サービスの総称の事を指す。
DeFiとは上の通り、『分散型金融』のことを指します。
分散型金融というのは、これまで銀行や証券会社が金融取引に介入していた現状を変えて、『スマートコントラクト』という技術を使って第三者を介入せずに取引を行うことを言います。
DeFiの最大のメリットは預金側の利子が増えるということです。
その理由は第三者機関(銀行、証券会社)が仲介することによる信用コスト、人件費、運用費を圧倒的に抑えることが出来るので、これらが預金者の利子に還元されるためです。
言い換えると、手数料が削減されるということです。
また、金融機関などの仲介者を通さずに金融取引が出来るようになった事で、口座開設の手間が省け国や地域に関係なく取引が出来るようになるというメリットがあります。
DEX
DEX
分散型取引所の事でオンチェーン(ブロックチェーン技術を使っている)である。CEXとは異なり、中央に管理者が存在しない取引所のこと。
DEXはDeFi(分散型金融)のアプリケーションの1つだと思って下さい。DEXは暗号資産の取引で使われる言葉です。
暗号資産取引では、Bybit,Coincheck,DMM Bitcoinなどの仮想通貨取引所(CEX)が主流だと思いますが、これらは全て企業が運営している取引所であり、『中央集権的』です。
一方、DEXは先ほどDeFiでも説明したスマートコントラクトを使う事で、管理者を必要としません。
その為、仲介料を支払う必要性がなくなります。
DEXの一種である『Uniswap』に関して以下の記事で詳しく解説していますので、お読みください。
CEX
中央集権取引所の事。DEXとは異なり、法人などの中央組織が管理、運営を行っている仮想通貨取引所の事。
さらに、口座開設の手間を省け、仮想通貨を入れるウォレットさえ持っていれば世界中の誰でも取引をする事ができるという利点があります。
またDEXはCoincheckなどの仮想通貨取引所とは異なり、アルトコイン(俗に言う草コイン)を多く扱っているのが特徴です。
その為、CEXでは取り扱っていないが、自身が今後伸びそうだと思ったコインを購入することが出来るのも魅力です。
しかしながら、DEXはブロックチェーンを利用しており、管理者がいません。
すなわち、これまで我々のパスワードを保管してくれた為、仮に忘れたとしても取り戻せましたが、DEXの場合は自身のWalletのパスワードや秘密鍵を忘れてしまうと、二度と開かなくなってしまうリスクもあります。
このように管理者が居ない分、自身で管理しなければならない点がデメリットです。
DEXの代表的なサービスは、『Uniswap』『Curve Finance』『SushiSwap』『PancakeSwap』などが挙げられます。
メタバース

メタバース・・・インターネット上にある仮想空間のこと。この仮想空間の中では、現実世界と同じような経済活動が行われる事が特徴的である。自分自身のデジタル上でのキャラクター(アバター)を使うことで他のアバターとコミュニケーションを取ることが出来る。
メタバースは上で説明した通り、ユーザーがデジタル上のキャラクターを作り経済活動、社会活動を送ることが出来る仮想空間のことを指します。
似た言葉に『VR』がありますが、メタバースは空間そのものを指すのに対し、VRは仮想空間によりリアリティさを上げる為に装着するものです。
そのため、メタバースを体験するのに、必ずしもVRを必要としないという事は知っておきましょう。
メタバースという言葉は、1992年にニール・スティーヴンスによって書かれた小説である、『スノウ・クラッシュ』を発端とします。
そして、実際にメタバース空間が作られたのは2003年のことであり、20年程前からメタバースは存在していました。
とりわけ、近年はコロナで在宅率が高まったことからメタバースでコミュニケーションを取る機会が増えてきており、ゲームのみならずビジネスへの活用も増加傾向にあります。
しかし、現在でもメタバースの利用率は低く(2022年12月時点での国内利用割合は5.1%)状況にありますが、利用したことは無いが認知しているのは全体の83%を占めているので、今後は利用率が上昇していくのは間違いないと言えるでしょう。
メタバースという言葉を知っている人(認知者)は全体の83%
そのうち他者に説明できるレベルで理解している人(理解者)は全体の12%弱(2022年6月時点では5%未満)
実際に利用したことのある人(利用者)は全体の5.5%
利用者のうち、月1回以上利用している人は全利用者の30%強
理解者、利用者ともに女性の割合は男性の4割程度
メタバースへの主要アクセス手段はスマホ・タブレット(6割)、PC等平面ディスプレイ(2割)で、「視聴型」のアクセスが中心。VR-デバイスのような「没入型」でのアクセスは、簡易型を含めても2割にとどまる
現在のメタバースの応用領域(複数回答)は、ゲームや音楽・ライブ、ショッピング等を挙げる回答者が多い。将来の応用領域についてもゲーム等を挙げた回答者が多いが、教育・学習、医療・健康、遠隔会議などへの応用を挙げた回答者が顕著に増加している。
三菱総合研究所(NRI)ホームページから引用
ゲーム関連のサービスだと皆さんもご存知の『マインクラフト』『あつまれどうぶつの森』などがあります。
マインクラフトは、マーケットプレイスを通じてアイテムを売りクリエイターが収入を得られるような仕組みがあります。
つまり、ゲームを通じて経済活動が行われるということを意味します。
『Minecraft マーケットプレイス』を通じて、欲しいアイテムを購入することでユーザーの体験価値を上げると共に、クリエイターが報酬を得られるという、Win-Winな関係を構築しています。
ビジネス関連の最近のサービスだと、Meta社が注力しているメタバースサービスである『Horizon Worlds』があります。
このサービスは、『Metaquest』と呼ばれるVR機器を装着を付け、仮想空間の中で様々なユーザーとリアルタイムで会話を楽しむことが出来るサービスです。
さらに、『Horizon Worlds』では、自身で仮想空間上でコンテンツを制作し、他のユーザに販売して収益を得ることもできます。
パーティ等のイベントに参加出来たり、仮想空間上で旅行を楽しめたりするなど色々充実しているのが『Horizon Worlds』の魅力と言えるでしょう。
また、2023年の下旬にはMetaquestの最新版である『Metaquest 3』が発売されることが注目されています。
その他の有名なメタバースサービスとしては、『The Sandbox』 『Cluster』 『VRchat』 『Fortnite』 『XR CLOUD』などがあります。
DAO

DAO
ブロックチェーン技術を活用した、分散型自立組織の事。中心に所有者や管理者が居なくとも、事業を行えるような組織。
『分散型自立組織』とは、中央にいる管理者(従来の組織で言う経営者)が不在であり、メンバー同士で意思決定をする組織の事を指します。
トップダウン型ではなく、誰もがフラットな関係性を築ける事がDAOの大きな特徴です。
DAOでは、主にブロックチェーン技術に加えて、下記の技術を利用する事で成り立っています。
それは以下の通りです。
ガバナンストークンが分からない方のために意味を説明すると、
ガバナンストークン
組織での意思決定のための投票権を得るために必要とするトークンの事。
ガバナンストークンはCEX(従来の中央集権的な仮想通貨取引所)のみならず、先ほど述べたDEXでも取り扱っている事が多いです。
DAOは身分や年齢、国籍などのバックグラウンドを考慮されないので、誰でも参加可能と言えるでしょう。
そして、2つ目のブロックチェーン技術を利用する事で、投票した記録や運営に関するチェーン上に記録されると同時に改ざんが非常に難しい仕組みとなっているので、透明性の高い組織を作る事に繋がります。
また、株式会社の場合は、財務諸表等を提出しますが、四半期や年度ごとに行われる決算発表の時にしか見ることが出来ません。
一方DAOはブロックチェーン技術によって、常に最新の財務情報にアクセスする事が可能である事が大きなメリットです。
Stable Coin
Stable Coin
仮想通貨の大きい値動きのリスクから回避するために、法定通貨(円やドルなど)に価値を固定させた暗号資産の事を指す。
上記の通り、ビットコインやイーサリアムを始めとした仮想通貨はボラティリティ(価格の変動幅)が大きい事が問題点としてあります。
すなわち、仮想通貨で何かを購入(決済)するとなった時に価値が暴落したら、決済手段として意味をなさなくなってしまいます。
これを防止する事を目的に『Stable Coin』は作られました。
また、Stable Coinは先ほど述べたDeFiでも使われることがあります。
Defiは中央に管理機関がいないため、従来の銀行で取られる手数料を取られないで済むと説明しましたが、ボラティリティが高いと元本割れするリスクがあります。
これを防ぎ、高金利を享受する手段として『Stable Coin』が使われています。
このようにStable Coinは、暗号資産の弱みであるボラティリティの高さを補うと同時に、ブロックチェーン技術の強みを持つ資産であることが理解できると思います。
種類としては『法定通貨担保型』 『仮想通貨担保型』 『無担保型』の主に3種類があります。(詳細に関しては、今後追加します)
Stable Coinの主な例としては、『USDT』『USDC』『JPYC』『TerraUSD』『Binance USD』などがあります。
ステーブルコインの詳細については下の記事も参考にして下さい。
Web3.0を取り巻く課題
法整備が不十分である事
特に日本の税制度はWeb3.0の普及を遅させています。例えば、暗号資産取引は『雑所得』に入るため、最大55%が課税されてしまいます。
また、法人の保有される暗号通貨の含み益にも課税がされてしまう現状も問題点です。
これが、Web3.0業界の起業家にとっては不利な状況であり、税制面が比較的整っている海外に流出してしまう原因にもなっています。
使いにくいサービスが多い
例えば、仮想通貨ウォレットである『MetaMask』に仮想通貨取引所から送金する手順は、初心者にとっては難しいです。
また、日本語対応されていないサービスもある状況です。今後は、初心者にとっても操作性の高い開発が注力されています。
深い知識・リテラシーが求められること
Web3.0はブロックチェーン技術を基盤とした概念ですが、そもそもブロックチェーンがどういうものなのか、自分の口で説明出来る方は少ないと思います。
さらに、暗号資産やNFT、またDAOなどのWeb2.0では触れてこなかった単語についても知識を深めないとならないので、学習のハードルが高いです。
逆に言えば今から知識を深める努力をすれば、周りと差をつけられるということです。
まとめ
今回の記事を通して、Web1.0、2.0、3.0の変遷を理解いただけたと思います。
Web3.0はブロックチェーン技術を基盤にしている概念なので、Web3.0に対する理解を深めるためにはブロックチェーンに関して知っておくことが重要です。
この記事の要点
- Web3.0は、ブロックチェーン技術を活用したインターネットの新しい概念のこと。
- Web3.0の特徴としては、従来いた中央管理者(Google ,Apple ,Facebook ,Amazon)がおらず、分散しているという事。
- 現在はWeb2.0とWeb3.0の過渡期にいる。
- Web3.0のトレンドの技術としては、『NFT』『暗号資産』『DeFi』『DEX』『メタバース』『Stable Coin』などがある。
- Web3.0は改竄されないというメリットがありつつも、『法整備が追いついていない』 『専門的な知識が必要』などの課題も多く存在する。